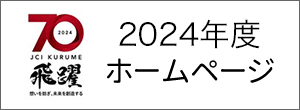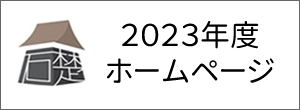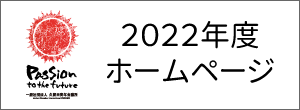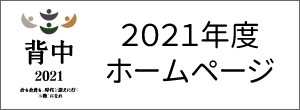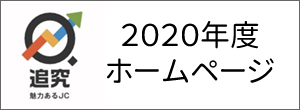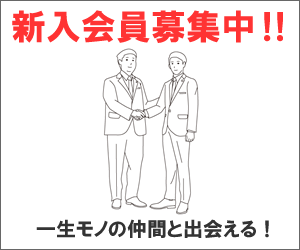2025年度 理事長所信
(一社)久留米青年会議所
理事長 橋本 栄次郎
Beyond Imagination
~想像を超える 未来を創造する~
はじめに
描いてみよう、30 年後の未来。
その未来の主人公である子どもたちは、笑顔でまちを歩いていますか。
輝こう、20 年後の未来。
その未来の主人公である我々は、まちをリードする人財へと成⾧できていますか。
では、10 年後の未来。その未来に、我々は何を託すことができますか。
遡ること約70年前。1954年、「明るい豊かな社会の実現」を理想とし、有志たちによって久留米青年会議所が設立され、この出発点から久留米のJC 運動は始まりました。「新日本の再建は我々青年の仕事である」とJC 運動を興した背景は変われども、時代の変遷や急激な社会情勢の変化とともに「明るい豊かな社会の実現」を再定義し、地域を憂い、住み暮らす久留米のまちを想い、果敢に社会課題と対峙してきた先輩諸兄姉の功績が、今日までの久留米のまちの発展を支えてきました。先人達が努力して築き上げてきた「今」を生きる我々は一体どんな未来を次代に紡ぐことができるのでしょうか。
その答えは、人それぞれであり、おそらくすぐに見つかるものではありません。
しかしながら、創立70周年を迎えた我々が、新たな時代を迎えに行くにあたりできることは、これまでの歴史に感謝するとともに、未来を見据え、想像力を働かせ、圧倒的な当事者意識をもって前向きに取り組むこと。これこそがこの問いの解に辿り着く最初の一歩、ではないでしょうか。
歴史的な一年を迎えた組織が新たな一歩を踏み出す2025年度、理事⾧としてのひと・まち・組織への想いをしたためさせていただきます。
共に歩む、2025年度。切り拓く未来を、創造しよう。
未来の「まちづくり」のために
青年会議所が持つ強みとは何でしょうか。普遍的な理念と時代に即したミッション・ビジョン。これまで展開してきた運動は社会の課題解決の一助となり、地域社会の発展に寄与する大きなうねりを起こしてきました。一方で、規律や既成概念に縛られ、画一的な運動に帰結している点も否めません。言わずもがな、運動を起こすのも、その運動を起こす組織を司るのも、我々JAYCEEであります。青年会議所のミッション・ビジョンには共通して「リーダー」という言葉が出てきます。理想のリーダー像を体現できる人財が集まった組織。一見強そうではあるものの、抽象的な表現であることも否めません。
理想のリーダー像とは何か。それは、守るべきものが明確にあり、身近にいる人々や自らが住まうまちの未来。現在のみならず、その未来を守るべき対象として、人やまちの未来を明確に捉えリードできる人財であると考えます。そのような人財の集合体こそが、理想の組織と言えるのではないでしょうか。未来を軸に、いまを生きる。そのような人財をこれからも育成・開発していくことこそが、ひとづくりを通してまちづくりを行う青年会議所の強さの根源であると確信しています。
【人財育成/人財開発】
約40年もの間、久留米青年会議所独自のアカデミー委員会が果たしてきた役割は、未来への礎として、毎年毎年新たな人財を育む機会として、脈々と受け継がれてきました。ひとづくりやまちづくりには、優先順位も優劣もありません。こと入会一年目の会員が所属するアカデミー委員会においては、JC 活動・運動の目的や理念に対して共感、を生み出す仕組みが必要となります。その時々で、会員一人ひとりが周囲に共感と影響の輪を拡げるリーダーの育成こそ、これからの次代のまちづくりにおける必要な人財であると確信しています。
また激動の時代と呼ばれる昨今は、VUCA(Volatility:変動性、Uncertainty:不確実性、Complexity:複雑性、Ambiguity:曖昧性)と称されています。予測困難な状況では、会員一人ひとりが自ら情報を収集し、状況を分析して、素早く適切な行動を取ることが求められています。なぜなら多くの課題や問題は、様々な要因が複雑に絡み合い、ネガティブな連鎖を起こしながら、私たちの地域に影響を及ぼす一方で、様々な要因を解決するためのアクションを起こし、波及効果を生み出すことこそが、ポジティブな連鎖をつくることにもつながると考えているからです。誰のために、何のために。正解が無い中で、組織としての向かうべきベクトルや大切にすべき価値観が共有されている仕組みを構築したその先に、地域や社会により良い変化を与える人財へと成⾧できると確信しています。
未来の「ひとづくり」のために
まちづくりとは何でしょうか。この解を紐解くにあたり欠かせない要素として視野を拡充することが挙げられます。青年会議所に入会してよく耳にする「機会の提供」。では、我々は果たして、機会を「享受」しに行っているでしょうか。主体性が求められる今日、能動的に視野を拡充する。そのヒントは、青年会議所の組織としての特性にあるように思います。
世界(JCI)には、100を超えるNOM(国家青年会議所)があり、我々と同じように、地域に根差した活動を行っている約14万人を超えるメンバーがいます。こと福岡県下、福岡ブロック協議会には約1100名、日本国内に目を向けても670を超えるLOM全体で、約2万4千人の会員が属しており、この数値が明らかにするとおり、視野を外に拡充することで得られるスケールメリットを感じてほしいと思います。ただし、スケールが大きいから「正」というわけではないことも忘れてはなりません。視野の拡充、とは外ばかり、内ばかり、ではなくどちらも、に目を向けることだと考えます。中を知り、外に出る。外を知って、中に取り入れる。ひとの豊かさも、まちの豊かさも、感性も視野も一旦外に拡げ、中を顧み、また外に展開する。この機会が身近にある環境こそが、まちづくりを通してひとづくりを行う青年会議所の強さの根源であると確信しています。
【地域共創/国際共創】
グローバル化・ICT化・地球規模の環境変化は、我々の地域においても、抱える課題・諸問題を複雑化させています。「社会的・国家的・国際的」な視点から地域を考える。「社会的・国家的・国際的」な視点から国際を考える。ローカルとグローバル、この両方の視点から、課題・諸問題をステークホルダーと協働で向き合うことで、未来を共に創り出す効果を実証していく必要があると考えます。
グローバルな世界に飛び込むには、多様性を受け入れることが必要です。ローカルな世界を誇るには、自らの住まう地域の魅力に気付くことが必要です。地域と国際、ローカルとグローバル。これらは対比構造、ではありません。物事を多面的に捉えるにあたり、ひととまち、自己と他者、国内と国外、など二元論で考えることは重要ですが、さらに重要なのは二者択一で解決するのではなく、二者を高い次元で統合する思考を持てるかということだと考えます。世の中は様々な矛盾で満ちていますが、その中で何かを実現しようとすれば、二面性の壁にぶつかるのが現実的です。ただし、これら二面性を否定せず、寛容することによって、「どちらか」の二項対立を乗り越え、矛盾を克服し、「どちらも」を実現する新たな価値を共に創る舞台が整うのだと確信しています。
未来の「組織」を支えるために
持続可能な組織に必要な要素とは何でしょうか。現在の久留米JCは、所属するメンバーの世代・職種・業種も多様化しており、メンバーの誰もが活き活きと活躍できる組織運営が必要です。多様なメンバーが活躍し、組織が活性化され、地域や社会により良い変化をもたらす運動を起こすためには、掛かるコストを意識しながら有意義なものにしていくことや、メンバーが参画しやすい環境づくりを行う必要があります。家族や仕事。これらの犠牲の上に、良い事業は成り立ちません。我々は、誰かに支えられて活動・運動ができています。その一番身近な「だれか」。その方々の理解・応援なくして、未来を描けるでしょうか。持続可能な組織を築けるでしょうか。
理解・応援していただく一番の解決策は「共感」を得ることだと私は考えます。メンバーの誰もが参画し活躍できることは、多くのメンバーの意思が反映された事業構築が可能となります。また、家庭や仕事を両立しながら活躍するメンバーが増えることは、周囲からの理解や応援にもつながります。さらに共に活動したいと共感を生む組織となることは、会員拡大にもつながると信じています。組織は人なり。会員数の拡大は、地域や社会により良い変化をもたらす組織の質の向上に不可欠です。そのためにも自らの志や会の魅力、そして組織の未来像を言語化することが必要です。共感の連鎖。支えていただいている家族や会社から、我々の活動する地域のステークホルダーから応援され、共感される組織こそ、持続可能な組織たりうると確信しています。
【トランスフォーム】
希望をもたらす変革の起点。こと青年会議所の組織においては、総務や規則といった会の下支えをする運営グループにその役割を担っていただきたいと考えます。ひとづくり事業もまちづくり運動も、盤石な組織運営が施されなければ成り立ちません。その盤石さを形成するには、目的と手段を見誤らないことだと考えます。例えばDX化。例えば効率化。これらは手段であって、目的ではありません。会議の数を減らすといった決して効率だけを求めるのではなく、効果の最大化を目指す中で生産性の向上を実現していかなければなりません。また久留米JCは近年、SNS等様々なメディアを介して発信力の強化に取り組んできました。事業等の発信は、久留米JCの活動や運動の認知にはつながっておりますが、より共感を生み出す発信を戦略的に行うことが求められていると考えます。発信する対象は誰か。発信した結果、どのような効果を創出したいのか。共感、をキーワードに魅力的な組織運営を実施いただきたいと考えます。
そして、その組織運営に華を添えるのが、事業構築の基礎となる規則・財政面の厳格さです。我々の活動・運動の原資の多くは、会員一人ひとりからの会費収入であり、シニアの諸先輩方からの補助金です。様々な要素が相俟って、安心して活動ができるのも、費用対効果の最大化に重点を置いた組織運営が必要不可欠であると考えます。率先垂範で会と向き合い、未来を見据え、物事に取り組む姿勢。ときに熱く、ときに冷静に。その一つ一つの行動が、活動が、周囲からの共感を生み、誇れる組織への変革の起点となると確信しています。
未来の「久留米青年会議所」のために
JC活動・運動の本質とは何でしょうか。社会課題解決団体。青年会議所をそう表現する人とよくお会いします。少子高齢化、人口減少、出生率の減少。都市部への人口集中、地方衰退はたまた気候変動、食糧不足に生態系破壊。さらには画一的な学校教育、⾧時間労働、インフラの老朽化。挙げるとキリがなさそうな日本の社会諸問題。この「現状」を前提として解決する手法こそが、まちづくり運動、と表現されており、ごもっともではありますが、抽象的すぎて、入会して間もないメンバーが同じベクトルで活動することができるでしょうか。
昨今、上場企業の多くが投資家等に自社の現状を示す資料として「有価証券報告書」ではなく「統合報告書」と呼ばれるアニュアルレポート、を自社PRの材料として開示している企業が増えています。この統合報告書の「色」は、企業によって様々ですが、統合報告書がスタンダードになった背景には「バックキャスティング」という手法が共通言語化されています。つまり企業は、理想や目標とする未来像を描き、その未来像を実現するためのプロセスを逆算し、未来から現在へ遡ってストーリーを構築する、という手法を取っているのです。この手法こそ、まさに我々青年経済人がこれから取り入れるべき考え方であり、このストーリー性こそが、青年会議所のまちづくり運動たる根幹であると考えます。市民・行政諸団体と手を携え様々な社会課題の解決に貢献してきた青年会議所だからこそ、視野を拡げ、パートナーシップの輪を拡充し、新たなまちづくりの未来を描くその先に、未来の久留米青年会議所の「かたち」は見えてくると確信しています。
【準備運動】
来たる2026年度、第54回福岡ブロック大会を主管します。この大会にメンバーが一丸となって取り組むことは、久留米JCにとって、大きな財産となると考えます。青年会議所の各種大会には、「益」という言葉を良く耳にします。LOM益、メンバー益、地域益、県益、そして社会益。誰のための福岡ブロック大会なのか。主役は誰で、どのような効果が求められ、どのような事業が必要なのか。視野の拡充。久留米JCと他LOM。久留米JCと福岡ブロック協議会。久留米市と福岡県内他市町村。近年強固になった福岡ブロック協議会とのパイプをさらに太く、濃いものとし、来たる2026年度に備える必要があります。大きな大会を主管するために、どのような経験値を積むことが必要でしょうか。メンバーが成⾧するためにどのような土台が必要でしょうか。大きな事業をメンバー皆で乗り越えたい、メンバーの自信と、組織への誇りを感じてほしい、久留米JCを次のステージへ進める一歩を踏み出したいと考えています。スポーツをされている方なら言わずもがな、準備運動の必要性
を理解できるのではないでしょうか。運動実施効果の最大化。これ即ち準備運動の最適化、だと考えます。福岡ブロック大会を主管するにあたり、2025年度を最適な準備運動の期間として過ごすことで、我々が主管する第54回福岡ブロック大会が必ずや素晴らしい大会となることを確信しています。
おわりに
我々の活動拠点である久留米市は、県内有数のポテンシャルを抱えているにもかかわらず、福岡市、北九州市と比較すると産業、社会動態と呼ばれる人口推移の視点においても、上り調子、とは言えないまちであります。一方で文化芸術的な素養が根付き、市内には300を超える医療機関数など、医療環境は全国でも有数のまちでもあります。そんなまちの特性を理解し、青年会議所の活動・運動の意義を、いま一度考えていただきたいと思います。私なりの解釈は、「メンバー一人ひとりの成⾧を通じてまちの発展に貢献し、それを未来へ紡いでいくこと」です。この志を強くもっています。そして何よりメンバーの皆さまがもつ各々の高い志こそが、久留米JC の活動・運動のエンジンです。まちを良くしたい。もっと成⾧したい。活動の動機は多様で構いません。ただほんの少し、周りに目を向け、視野を拡げ、来るべき未来が、明るく豊かで彩りあふれた「ひと・まち・組織」となりますよう、共感の輪を拡げ明確な志をもって行動していこうではありませんか。
人は一人で生きられない。これほどシンプルなことを忘れなきよう。
楽なことばかりを凝視せず、厳しいことから逃げ出さず。
困っている人がいたら助け合おう。問題が起これば皆で考え乗り越えよう。
自分らしく、難しい局面こそ、シンプルに。
たまには一呼吸おいて。たまには普段知らない世界に飛び込んで。
感謝と誇りと謙虚さと。
人生・JC、それぞれの目的を見失わず、前向きに。
Beyond Imagination
想像を超える 未来を創造する